2010年團 伊玖磨作曲/木下順二原作 歌劇「夕鶴」、
2011年 G. プッチーニ作曲 歌劇「ラ・ボエーム」、
2012年 尾上和彦 作曲 オペラ「月の影」-源氏物語-
と回を重ねてきた春秋座オペラ。
今年は、いよいよ、 G. プッチーニの名曲『蝶々夫人』を上演いたします。
公演に先立ち、6月上旬に楽屋にて行われた記者発表会の様子を少しだけ、
お届けいたます。
進行:舞台芸術研究センター プロデューサー橘市郎
- 橘
- 春秋座でやるオペラの目的に 「2つの高い」を取り払いたいというのがあります。 一般的に、「オペラは敷居が高い」と言われており、 もうひとつは「料金が高い」。 現在、日本でオペラを観るには何万円も払わないといけないですよね。 ですから学生は、到底観るチャンスがない。 この「2つの高い」を取りのぞき、 より、多くの人に観ていただきたいと思っております。 春秋座は、市川猿翁(三代目猿之助)が 「歌舞伎とオペラが理想的にできる劇場」として建てた劇場です。 ですから、この『蝶々夫人』は歌舞伎劇場の特性を生かしながら、 他のオペラ劇場ではできない演出をお願いし、 出演者の方々にも繊細な表現をしていただけたら、 という思いで企画しました。 春秋座のオーケストラピットは普通40~50人、入るのですが 花道を付けて使うとなると、それだけ入りませんので、 オーケストラの編成は春秋座独特の工夫をしています。 歌手の方々も第一線で活躍している人たちばかりで、 春秋座オペラに最多出演いただいている 川越塔子さんも今回、参加いただいています。 おかげ様で回を重ねる毎に、お客様が増えてきまして、 今年は先に学生席が売れ、ほとんどないという状況です。 ある意味、私たちが狙っていることが実現できつつあります。
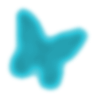
- それでは、私の方から公演監督、指揮者、演出家をご紹介したいと思います。 まずは『ラ・ボエーム』の時も公演監督をお願いした松山郁雄さんです。 今回は、出演も兼ねていただいております。
- 松山
- 橘さんとは以前から、劇場の雰囲気からしても 日本を題材にした「『蝶々夫人』をいつか春秋座でやりたいですね」s というお話はしておりました。 この作品は日本を題材とした特殊といえば、特殊な作品なのですが、 まぎれもなくプッチーニ作のイタリアオペラで、 当然、イタリア語で歌うわけです。 初演こそ失敗したそうですが、 今となっては世界中で何回も上演されている プッチーニの中でも代表的なオペラです。

- ただ、今回は日本で日本を題材にしたオペラを、 日本人の出演者、指揮者、演出家で、 日本人の観客のためにやる。 れっきとしたイタリアオペラではありますが 日本人の聴衆に満足してもらわないといけない。 このことは日本人がやる時に 大きな意味合いがあるのかなと思います。 そういう意味でも春秋座の機構は打って付けだと思いますし、 その意識で望みたいと考えています。 オペラは見えないところに沢山の人が動いていますから お金のかかる芸術だといっても過言ではありません。 日本でもバブル時代、沢山のお金を使って、 作り手の思いだけで豪華な舞台を作っていた時がありました。 今は厳しい時代というのもありますが、 そういう時代は去ったのかなと思います。 作り手のロマンだけでやるのではなく、お客様目線、 観客の立場に立ったオペラ作りに変わってきている気がします。 今回の作品は「1万円未満でリーズナブルに楽しめるオペラを」 と謳っています。 ということは製作費もコンパクトな中でやらなくてはいけない。 お金をかけないことをいい訳にせず、 だからこそ登場人物一人、一人の中身がきちんと作られていて 「日本人のためのイタリアオペラ」というのを くっきり、はっきりできたらいいなと思っています。 そこに向かってがんばって、やっていきたいと思います。
- 橘
- 20年前にジョン・ケアード(カナダ出身のミュージカルの演出家)が 『ミス・サイゴン』の舞台に本物のヘリコプターが出てきた時、 「豪華な衣装、お金を沢山かけた舞台というのは、そろそろ限界にきている」と、言っていました。 それを受けて、彼が『レ・ミゼラブル』を作った時に、 「良い脚本、良い曲、良い出演者、良いスタッフを揃えて、 そこで勝負するのが本当だろう」と言っています。 これは、まさしく我々が狙っていることと同じです。 春秋座オペラは「1万円未満で感動を」というのと、 良い指揮者、演出家、出演者がいて、 プッチーニの『バタフライ』の魅力はどこにあるのか、 ということを絞っていった時、良い成果を上げると思っております。

- それでは、指揮者の牧村邦彦さん、お願いいたします。
- 牧村
- 前回、『ラ・ボエーム』の時も指揮をさせていただいたのですが この劇場は花道を使うとオーケストラピットが 非常に狭くなってしまうのですね。 そういう意味で、今年もオーケストラの人数を 通常より減らさなくてはならず、 春秋座バージョンといってもいいぐらいの人数で演奏します。 サウンド的には、CDで聴くような 絢爛豪華な音はしないところもありますが、 その分、凝縮された良いサウンドが出てくるのではないかと 楽しみにしています。

- 『蝶々夫人』の初演は1904年なのですが、 先ほど松山さんもおっしゃった通り、大失敗だったんですね。 もちろんプッチーニのことが大嫌いな聴衆が邪魔をしたとか、 作品が良くなかったとか言われていますが、 僕は1904年バージョンを関西で初演し、 改訂された1905年の楽譜は多分、 こうであろうというバージョンも上演しています。 僕は『蝶々夫人』には、こだわりがありまして、 初演から少し改訂したバージョンでずっと続けています。 これは普段、上演される「現行版」という譜面より 少し改定した形で演奏しているのですが、 このバージョンは、かなり日本人、東洋人が蔑視されていて、 ピンカートンというテノールが蝶々さんに 随分と、ひどいことをするのでございます。 その辺りをクローズアップするには、 このバージョンが良いのではないかと思っています。 またピンカートンがアメリカに帰った後に結婚する妻・ケイトは、 「現行版」の2幕2場では、しゃべる所は数小節しかないんです。 でも初演版では、すごく長くしゃべっている。 彼女が長くしゃべるがゆえに 蝶々さんの悲劇性がより増していくという・・・。 僕にとっては、とても説得力のある書き方をしているので、 そちらを使用しています。 ピンカートンは、ひどい人なのですが、 ケイトは輪をかけてひどい・・・、 それは冷酷とかではなくて、とても正義感が強い・・・ 正義感の強い人の象徴みたいな女性です。 ピンカートンと蝶々さんが再会した時、 初演版では、ピンカートンはアリアを歌わないのですね。 実は胸から財布を出して「これで何とかしてくれ」って言うのですよ。 それはあまりにもひどい、ということでカットされたんです。 それで、後悔のアリアを歌う、 というのが現在のバージョンです。 そしてケイトの冷たい正義感が聴衆の涙を誘ってしまう。 そのシーンはどうしても入れたかったのです。 さらに今回は、僕がやってきた初演版に近いバージョンと この春秋座という場所に一番そぐった コンパクトで凝縮されたバージョンとして 手を入れて、新たに作ってみました。 それにより、松山さんがおっしゃった、 作品の神髄のようなものが、なおさら理解できるのではないかと 自負しています。 ですので、音楽としても楽しんでいただきたいと思います。

- 橘
- それでは演出の井原広樹さんお願いします。
- 井原
- 今回の舞台美術は、まず障子がドーンとありまして、 それがハーフミラーになっています。 それにも象徴されるように、 オーソドックスな写実的美術ではありません。 ですがジャパニーズ感を出し、 かつミニマリズムな感じで、やりたいと思っています。 それと、いけばなの未生流笹岡家元の笹岡隆甫さんに ご協力をいただきまして、笹岡さんが生けた大きな作品を後ろに置き、 「モダンな松羽目」というような雰囲気になれば、と思っています。 キャストの皆さんには、 比較的、制御された少なめの動きでやっていただき、 舞台における、一つのフォルムの中でやっているように 見えたらと思っています。 この作品は日本人とアメリカ人が出てきますが、 音楽はイタリア音楽で、歌唱はイタリア語。 普通の戯曲の感覚でいくと、難しい世界ですが、 見ている分には何も思わないですね。 あたりまえの世界のように感じます。 そんな風に、この舞台の雰囲気を含め全てが 一つのフォルムの中で成り立って見えればいいなと思っています。 先ほど、舞台はシンプルでなければいけない、 という話がありましたが、そういう意味では ピーター・ブルック(イギリスの演出家、演劇プロデューサー、 映画監督)が作る作品のように「なにもない空間」というふうに お客さんに見えればいいなと思っています。 歌手の皆さんは、本当に力のある方ばかりなので、 そこは、間違いなく今回のポイントだと思うのです。 スター歌手ばかりです。 そういう意味では、お料理のように 素材の持ち味がそのまま出れば 良い公演になると思いますので、 そこが損なわれないようにするのが、 私の仕事の大きな部分だと思います。

- 『蝶々夫人』を語るとき、 日本のとらえ方というのが一つの議題になりますが、 やはり、プッチーニは日本に来ないで『蝶々夫人』を書いた というのは大きな事だと思います。 この作品の中には沢山のテーマが出てくるのですが、 ミラノにいる総領事館夫人から入手した様々な資料を、 組み替えて作ったのだと言われています。 たぶん、プッチーニも日本を見なくて書いたという怖さより 作品における「ファンタジー」に 重きを置いたのではないかと思います。 この作品が書かれたのは 『トゥーランドット』や『イリス』とか エキゾチックな作品が沢山出た時代ですので プッチーニ独特の 「自己犠牲をメインとする主役」 が、活躍できる場を探したら、それが日本だった。 日本人の女性が、 彼好みの「見返りを求めない自己犠牲のヒロイン」に マッチしたのだと思いますし、 彼にとっても日本がファンタジーの国であったのだと思います。 日本に対する誤解を修正した『蝶々夫人』を 上演している舞台もあります。 私自身、イタリアに留学した時、先輩たちに 「『蝶々夫人』だけは観てはいけない」と言われていたので、 大分たってから『蝶々夫人』を観たのですが、 確かに演出的なことでいうと初めに「あっ!」って思うのです。 しかし、観ていると悪い意味でのショックは薄れていって、 プッチーニの音楽に埋もれていくというか・・・ ひとつのマテリアルとしてとらえて 蝶々夫人の悲劇性を高めている。 とある日本の大歌劇場のプロデューサーが 「『蝶々夫人』だけは、やりたくない。 なぜなら日本人女性をあまりにも馬鹿にしている」と言ったのですが、 その言葉に納得いったのが半分。 でも、戯曲の中では人種差別などに 満ち溢れているとは思いますが、そういうことをセーブするより、 作品のドラマの方に目を向けた時、 人種差別という問題は、後ろの方に追いやられると思います。 決して、解決すべき問題ではない。とは申し上げませんが、 それ以上のものが前に出てくるのではないかと思います。
