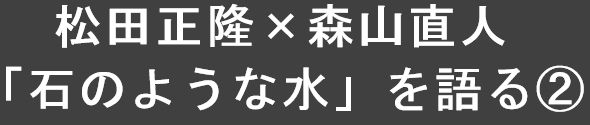『石のような水』プロローグイベントを、 10月19日より1週間 元・立誠小学校 特設シアターで開催。 タルコフスキーの映画作品『ストーカー』『惑星ソラリス』、 維新派・松本雄吉氏の『蜃気楼劇場』、 松田正隆氏出演のテレビドキュメンタリー 『CAMOCEЛ(サマショール)―長崎そしてチェルノブイリ』の上演に加え リーディングやトークイベントなどを行い、盛況を得ました。 今回は作家・演出家の松田正隆氏に 『石のような水』を書くこととなった経緯や構想、作品への思いを伺いながら、 演劇批評家・森山直人と「その後」について語りあった トークの様子をご紹介します。
- 森山
- 先ほど、みなさんには、タルコフスキ―の『惑星ソラリス』と
ドキュメンタリー『CAMOCEЛ(サマショール)
―長崎そしてチェルノブイリ』をご覧いただきました。
『CAMOCEЛ』についてお伺いしたいのですが、
これは1986年、タルコフスキーが死んだ年であり、
チェルノブイリ事故が起こった年のちょうど20年後に
松田さんが実際にチェルノブイリにインタビューに行かれて
撮られたドキュメントなんですよね。
松田さんが代表の「マレビトの会」を立ち上げたのが、
大体、同じ頃だと思うので、その後の長崎3部作、
そして今回の『石のような水』につながっていく
原点の一つになっていたのだと思います。
改めて、今、いかがでしょうか。
久しぶりにご覧になったと思うのですが、
『CAMOCEЛ)―長崎そしてチェルノブイリ』
2006年/制作著作:テレビ西日本
★2007年フランスドキュメンタリーコンクールFIPATEL入賞/2007年度ロシアドキュメンタリーコンクール入賞 1945年、原爆によって多くを失った長崎。1986年、原子力発電所の事故によって都市自体を失った原発の町プリピャチ※。劇作家・松田正隆が二つの都市を訪ね、核が人々とふるさとに与える巨大な傷、断絶を描く2006年に放送されたドキュメンタリー番組。チェルノブイリ原発事故に大きな衝撃を受けた写真家・手島雅弘さんは13年後に様々な困難を乗り越えてチェルノブイリに入り、人と街の現状を撮影した。その時に撮影された高校生の集合写真を手掛かりに、長崎出身の松田と手島さんはチェルノブイリに向かい、4歳で被曝してスラヴォーチッチ※に移住、いま結婚や出産の時期を迎える若者たちにインタビューを試みる。黒木和雄
1930-2006 映画監督。松田正隆による戯曲作品『紙屋悦子の青春』を黒木和雄監督が映画化している。サマショール
チェルノブイリ原子力発電所事故後、立ち入り禁止区域とされた土地に、自らの意志で暮らしている人々。 - 松田
- そうですね、2011年に福島のことがあった時 同じようなことを取材したことがあるなあと思い出したんです。 それから観てみようと思っていたのですが、なかなか観られずに、 今日、意を決して観ました。いろいろ考えさせられました。 このドキュメンタリーを撮ることになったきっかけは ディレクターの馬場明子さんが 映画監督の黒木和雄さんと面識がありまして 黒木さんのドキュメンタリーの手法を学んだり、 影響を受けておられたそうで、 黒木さんにチェルノブイリのドキュメントを撮りたいと相談したところ 僕の名前が出たそうなんです。 最初は僕に構成作家として参加してくれと言われたんですが 構成作家としてもチェルノブイリに行きたかったし、 原爆のこととかも演劇で作っていきたいと思っていたので 「行かせてください」と話をしていたら、 「じゃあ、インタビュアーとして行ったらいいのではないか」 ということになったんですね。 それで、私の方からも「ふるさと」という問題を もう少しフィーチャーしていきたいと言ったら サマショールという人がいると、教えられまして、 その人たちの思いとは、一体なんなのだろうとか思ったんです。 例えば、原子力事故で都市自体を失った街プリピャチ※に4歳まで居て、 その後、強制移住で他の土地に移った若者達は、 プリピャチをどういう風に思っているのか。 故郷を捨てた若い人たちは、記憶の中に故郷を持っているのですが、 サマショールのお爺さんたちは、故郷は記憶ではなく現実。 彼らのそういう思いに加え、ドキュメンタリーでは、 長崎の被爆者、片岡津代さんの体験談も入ってくる。 50分ぐらいの作品なのに、非常に要素の多い内容になったと思っています。 ただ、それを貫通しているのが、 「ふるさと」をどう捉えるかということなんです。 その「ふるさと」にまとわりついて自動的にやってくる ノスタルジーに対して抗いたいみたいな気分もあったし、 僕としては「ふるさと」に対してもう少し可能性… ふるさとが異郷になるような可能性といっていいのか、 そういうことをドキュメントの中に盛り込みたいという思いがありました。
- 森山
- 要素が多いというのは、そのとおりだと思うのですが 実際に「ふるさと」という捉え方は、 ドキュメンタリーに出てくるひとり一人によって違うという感じがしました。 サマショールの人たちは、立ち入り禁止区域であろうと そこに住むのは当たり前だと。 彼らにとって、ふるさとというのは体の一部みたいなもので、 当然のものとしてそこにあるし、 改めて、それは崩さないということを決意している。 それに対して4歳ぐらいで被爆し、 プリピャチを故郷だと言う人たちは、すごく揺れている。 「ふるさと」ということを、そもそもどういう風に考えるべきなのか。 サマショールの人たちと違って、 「ふるさと」とは、ある意味、抽象的になってしまった ということもあると思うんです。 テレビで放映するにあたり、ある程度、編集されているので 伝わらなかった部分も、たくさんあると思うんです。 そういうものも含めて、それぞれのふるさとの認識、 身体化のされ方の違いって、当時、松田さんはどのように思いましたか? あるいは、今は、どのようにお考えですか?
- 松田
- うーん…。いずれにせよ、分からなかったんですね。 とにかく、どういうことなんだろうなって。 若者たちの身体感覚的の中にある「ふるさと」の記憶と そこが汚染地区だと分かっていながら、 避難地域にいるとストレスで死んでしまうから それなら故郷で死ぬ方が良いっていう老人達の感覚ですね。 分からなくていいと思いますし、分かるものじゃないと思いますが 言葉として出てきたり、話すときの身振りなどで、 潜在化している思いが顕在化するんじゃないかと、 それがインタビュアーの役目だと思ったので聞こうと思ったのですが。
- 森山
- でも、いきなり行ってわかるものじゃないですよね。
- 松田
- それに、取材班の身体感覚も奇妙なものになっていったんですよ。 なんかね、あの時のことは、変な風に思い出されるんですが、 ある意味、ちょっとした緊張感というか。 30キロ圏内でも検問があったり、膨大な敷地が広がったりしていて。 そういう場所に慣れるまで随分、時間がかかったし 慣れた頃には帰国しなくちゃいけないし。
- 森山
- ええ。
- 松田
- サマショールのお宅に行くと、必ずご当地のものを振まわれるんです。
 ドキュメンタリー『CAMOCEЛ(サマショール)
―長崎そしてチェルノブイリ』より
ドキュメンタリー『CAMOCEЛ(サマショール)
―長崎そしてチェルノブイリ』より- 自家製のウォッカもあるんですが、ウォッカはアルコールだし、 そんなに汚染されていないから大丈夫だと思うんですが、 「地酒です」的なことを押してくるわけです。 ジャガイモとかもね。もちろん食べてたんですが、 一番、怖かったのは、キノコの漬けてあるもの。 「この辺で採れたキノコです。本当に美味しいから食べなさい」って 言われたときは、ちょっと…。 でも食べましたよ。 でも、そういう科学的に証明されていることよりも、 あそこに入った時の、なんていうんだろう、 こういう言い方をするのはいけないですが、 汚れたところに触るような雰囲気はあるんですよ。
- 森山
- それは空気として。
- 松田
- ええ。空気としてあるんです。 放射能とかは見えないんですけれど、 測ってみると29マイクロシーベルトとかありましたからね。 びっくりしましたけれどね、 福島でも0.1ぐらいで高いと言われるのですから。 あれ、苔みたいなところで測ると上がるんです。
- 森山
- 色々なところでやってみたんですか?
- 松田
- ええ。線量計みたいなのを渡されて
- 森山
- シーベルトなんて、その頃の日本人はほとんど知らなかったですからね。
- 松田
- でもちょっとした茂みとかね、そういうところに行くと急に数値が上がって、 ピーピー鳴ることもありました。 でも、なんだか他人事なんですよ。それは覚えています。 取材している時の感覚は他人事でした。
- 森山
- でもドキュメンタリーの中で、他人事じゃない人という役割を 負わされているところがあるじゃないですか。長崎出身ということで。 でも松田さん自身も長崎に原爆が落ちてから20年近く経ってから 生まれている世代なわけですし、 むしろ松田さんの感覚に近いのは、 プリピャチの高校生たちの方かなと思ったのですが。
- 松田
- そうですね、長崎の被爆の問題というのはあったみたいですし。 僕の家族には特に無かったですけれど、ただ長崎に住んでいるというだけで、 なんですか、姉も兄も調べられるというのがあったみたいです。 でも、もっと被爆されている二世の方ですとか、 被爆を受けた人の被爆差別というのはあったと。 それは取材に行く時に頭の片隅にはあったような気もします。
- 森山
- 観ていて思ったのは、長崎の浦上天主堂に被爆マリアを飾るというところ。
 ドキュメンタリー『CAMOCEЛ(サマショール)
―長崎そしてチェルノブイリ』より
ドキュメンタリー『CAMOCEЛ(サマショール)
―長崎そしてチェルノブイリ』より- 一つの原爆の放射能の「記憶」の仕方だと改めて思ったんですね。 ただ、それは外国から落とされた原爆であるということで ある意味、割とポジショニングをハッキリさせられる。 被爆者と被爆国というのが割と結びつきやすい。 それに対して原発事故というのは国家的なレベルで言うと 自分が自分を傷つけるものですよね。 そういうものというのは国家レベルでは位置付けにくい。 最近、福島をどうやって忘れるかという動きというのは、 ある意味、そういうものの表れかと思うんです。 位置付ようもない。 チェルノブイリの場合、キエフにチェルノブイリ通りや記念碑がありますが、 あれは、ある種、自分で自分を傷つけた国家が問題を どういう風に「記憶」するのか、メモリアルを作るのか、 ということが出ていたと思います。 その辺、日本はこういうものを作るのかなあ、どうするのかなと思いました。 僕はチェルノブイリに行っていないので分からないのですが、 サマショールの人達ではなくて、 もっと一般的なチェルノブイリの受け止め方。 20年たって、どういう風に記憶しようとしているのか。 そういうことに関して、現地に行った時にお感じになったこととか。
- 松田
- パッとは言えないですけれど… 確かに自分たちの起こした出来事の記憶を どうメモリアル化していくかという問題ってありますよね。 ウクライナは大統領が変わった頃で、そういう意味もあって、 事故について検証をしたり、ドキュメンタリーも作られていたのではないかな。 このドキュメンタリーをコーディネイトしてくれた人も 4号炉にも入ったりしてチェルノブイリのドキュメンタリーを作ったそうで ソ連時代の誤りみたいなものに対して 批判を加えることをやってきているだろうし。 もちろんチェルノブイリの位置付け方が ロシアにしてもウクライナにしてもうまくいっているのか別として、 とにかく向き合おうとしている。 記憶のあり方としてね。これからの問題としてありますよね。
- 森山
- 確かチェルノブイリの直後にマレビトの会でなさったのは、 『アウトダフェ』じゃないかな。

- 松田
- そうですね。まさに、この後。
- 森山
- あれは舞台に巨大な穴があるっていう芝居でしたよね。
- 松田
- 結構、この体験に影響されて作りましたね。
- 森山
- その後にずっと作っていく長崎3部作のような中でも、 ある所では坂の大きな装置があったり、 あるいは広島の平和公園という公園であったり、 ある種、土地と身体を繋げるような何かですよね。 全部、何か僕は穴のバリエーションみたいな気がするんですよね。 それはつまり、まさに「身体と土地を繋ぐ」接点として 穴があったり坂があったり、公園があったりする流れがあって、 それと「メモリアル(記憶)」という問題が すごく重なりあっている感じがするんです。 それで、ちょっとだけ今回の、『石のような水』のことを。 これは、久しぶりにお書きになった長編ドラマですけれど、 その「記憶」の問題を別の側面から扱っているように思いました。 松田さんにとって、長崎3部作とか、 マレビトの会でやってきたことと、今回の作品の繋がりみたいなもの、 感じられていますか?
- 松田
- 映画の『ストーカー』の中で隕石が落ちてゾーンができる。 そのことやチェルノブイリのこと。 つまり、私たちの計り知れない出来事が先に起きるけれど 私たちの浅い知識レベルでは、 それは軽い決定論的に因果関係が図れるわけです。 こういう動機があって結果があると。 浅い意識や、意識しないで行う社会的な日々の事、 歯をみがいたり、朝起きて通勤したりとか、 ある因果律の元で自動的に私たちは日々を生きているわけなんですが、 そういうのとは違う出来事が急に起きる。 普通に生きている時には、計り知れない、因果律の分からない出来事が…
- 森山
- ええ、突然、何かがおきる。
- 松田
- ええ。その時に人間というのは、それにつき合う時に 深層心理とか自分の身体の中に潜在している記憶が、 自分でも計り知れないし、 でも、何か普段生きている時の意識のタガが外れると まあ、夢なんかもそうですが、 自動的に生きている自動人形のようなものが、そうじゃなくなる。 深層心理みたいなものとくっついちゃう。 違うアレンジが生まれてくる。 そのようなものを空間と時間の関係の中で描きたいというのが、 今度の戯曲に込めた思いだったんです。 だから圧倒的にゾーンがあると。 街の近く、首都の近くに。 でも日々の普段のたわいのない会話が交わされている。 でもその時に、急に忍び込んでくるゾーンの深層心理みたいなものとのアレンジ、 そういうものとの相互作用みたいなもので 作品が作れないかなと思ったんですね。 タルコフスキ―の映画は、カメラと一緒にストーカーがゾーンに行きますが、 演劇の場合はなかなかね、一緒に行っちゃうことはできないので、 普段の会話の中にシュッとゾーンが混在するという。 それが、あられもないものとくっついちゃう。 例えば、ラジオの声とくっついてしまったり、それが恋愛と絡むとか。 SFなのかメロドラマなのか分からない、というものになればなと。 でも、上演するのは難しいのかもしれませんね(笑)。
- 森山
- でも、脚本を読んでいて、 穴とかね、そういうようなものが身体の中に入ってきた、 という感じが、すごくしました。 先ほどのドキュメントを見て気がついたのですが、 放射能っていうのは数値化するといっても 今の科学では数値化しきれないということですよね。 そうすると必然的に放射能というものをどう捉えるか、考えるかって 全部、その人の内面に全部押しかかってくる。 その感じが、日常的なちょっとした事にも重み・・・、歪みかな 一つのことが新しく終わることで形が変わっていく。 今までこういう形だったのが、形が変わって内面の中に表れていく。 その中で普通の恋愛とか生活というものが どういう風に形が変わっているのか、歪んでいくのかということを、 今回、テーマにしているような感じがしました。 ある意味、放射能というものを間近に受けた時に、 それ以降の生活とか恋愛とかどんな風に変わっていくのか、 そういう気がしました。 書くのに時間がかかりました?

- 松田
- 随分、かかったと思います。ポンポンポンと書ける感じじゃなかったですね。 物語として書ける感じはしなかったので、 誰かと誰かが会話をしている、短くてもいいので会話が並列していくと。 いわゆる葛藤ってドラマになると思うんだけれど、 そういうところは気にしないで、 どちらかというと会話と会話によって起こった出来事を、 「しりとり」みたいな感じにしてやっていくような感じ。 「しりとり」というのかな…。 次のシーンにちょっとだけ影響して、 それが電波されていくみたいなことが、物語の起伏としてあると思いますが。 だから、なかなか終わりが見えないというか。
- 森山
- 松田さんの戯曲では、登場人物がいて、 ある種、リアリスティックなことをしゃべっている会話劇は 久しぶりだと思うのですが。 例えば、『海と日傘』とか『紙屋悦子の青春』とか、 時空劇場でお書きになっていたようなドラマとはまたちょっと違う。 ああいうものは、終わりがハッキリあるドラマだったし、 終わりが非常にノスタルジック、かつ抒情的に、ぐーっと際立ってくる。 今回の「ゾーン」というものって、どこにもいけない。 終着点として、どうにも機能しないものであるから ある意味、終われないことが前提になっているような 書かれ方をしているなと思って。 例えばマレビトの会の演劇は、簡単にいうと非リアリズム、 反リアリズム演劇だと言えるかもしれないけれど、 そういうものとは違った演劇になりそうな気がしました。 新しい松田さんの局面みたいなものをハッキリ感じました。
- 松田
- プリピャチという都市、街を観たのは大きかったですね。 原子力に携わる人たちの未来都市みたいな街。 プールもあって遊戯施設もあって、若い技術者もいっぱいいる、
 ドキュメンタリー『CAMOCEЛ(サマショール)
―長崎そしてチェルノブイリ』より
ドキュメンタリー『CAMOCEЛ(サマショール)
―長崎そしてチェルノブイリ』より- エリートたちの街が平原の中に突然現れる。 高層ビルやアパートが林立して、 都市の理想形としてできたんでしょうけれど、 それが一瞬にして廃墟になる。 あのような都市がずっとゾーンの中にあって、 何が驚いたかというと、廃墟というのは崩れ落ちるというのではなく、 自然が繁茂するんだなっていうこと。 60年間草木は全く生えないといわれたのに、すぐ生えてきたらしいのです。 チェルノブイリの街にも生えていて、それが不思議でした。
- 森山
- そういうのは行ってみないと分からないですよね。 最近、東 浩紀(批評家・小説家)さんが、 チェルノブイリは全く無人の場所ように思われているけれど、 ものすごい沢山の人が日常的に働いている。 それは行かないと絶対、分からなかったといってました。 まさにそういうようなこと沢山あるんじゃないですかね。
- 松田
- ドキュメントにもスラヴォーチッチ※という都市が出てきましたけれど、 あそこから通勤している人が沢山いて、 廃炉にするためには何年もかかるから、そこで働かないといけないんですね。 いくら、あそこが電気を供給していないとはいえ ずっと維持していかないといけない。 あの近くにホテルもあるんです。 僕らもそこに泊まったんですが、夜は星空がすごかったです。 そんなことは思い出話ですけれど。
- 森山
- それにあれだけ空が広いとね。廃墟の上から見た眺望はすごいですよね。
- 松田
- 映画『ストーカー』の中で、 30キロ圏内の草木の中に寝転ぶシーンがありますけれど、 あの感じ、分からなくもないな。 自然というのが、どんどん押し寄せてくというか。廃墟といのは。
- 森山
- ゾーンは自然が繁茂していると。
- 松田
- そういうのが、プリピャチの周辺を歩いた時に感じたことでしたね。
- 森山
- 時間がきてしまいました。 ぜひ、『石のような水』にお越しいただけたらと思います。
松田正隆プロフィール
劇作家・演出家。マレビトの会代表。1962年長崎県生まれ。89年立命館大学文学部哲学科卒業。96年『海と日傘』で第40回岸田國士戯曲賞、98年『月の岬』で読売演劇大賞最優秀作品賞、98年『夏の砂の上』で読売文学賞、2001年に京都府文化奨励賞を受賞。2003年より演劇の可能性を模索する 集団「マレビトの会」を結成。主な作品に『cryptograph』(07)、『声紋都市-父への手紙』(09)、写真家笹岡啓子との共同作品『PARK CITY』(09)、『HIROSHIMA-HAPCHEON:二つの都市をめぐる展覧会』(10)、『アンティゴネーへの旅の記録とその上演』(12 などがある。現在、立教大学現代心理学部映像身体学科教授。戯曲の他、『美しき夏キリシマ』(03)、『紙屋悦子の青春』(06)など、映画の脚本・原作も手がける。