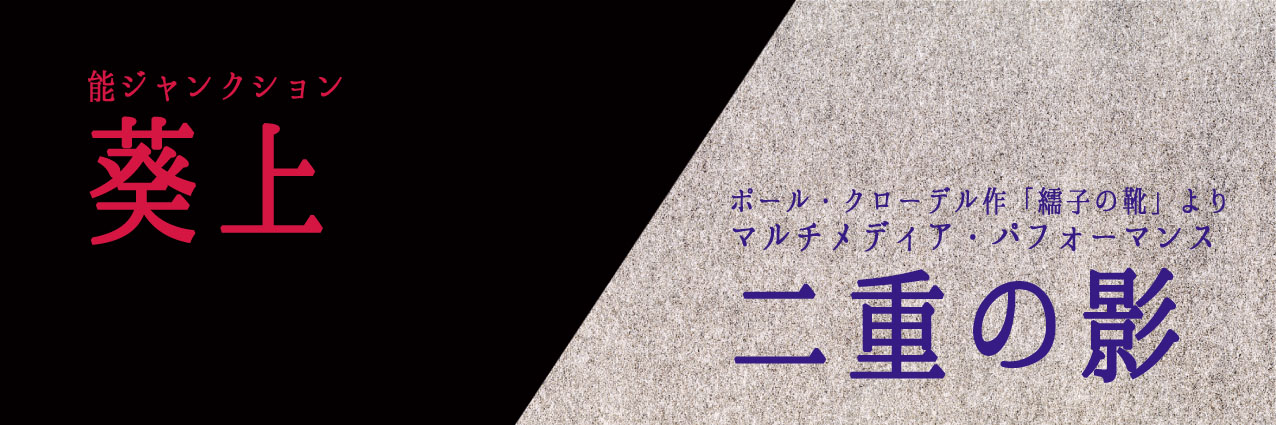
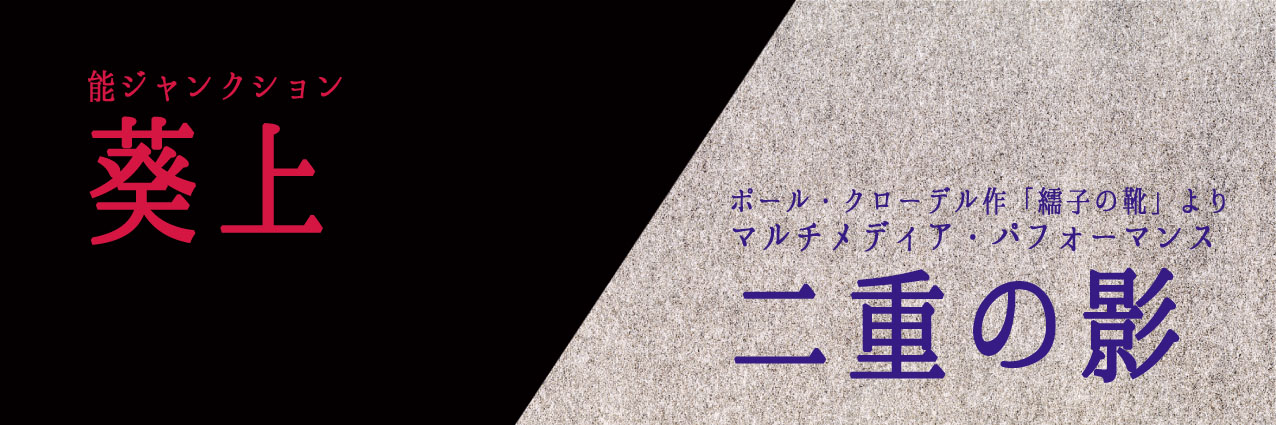
『葵上/二重の影』演出助手 木ノ下裕一(木ノ下歌舞伎主宰)
しばし、机の前で途方に暮れております――。
今月末に行われます『葵上/二重の影』について、その見どころについて書いてくださいというご依頼なのですが、舞台芸術研究センターさんが私を買い被ってくださっているのか、どんな駄文でも無いよりはマシだとお思いになったのか、そこのところはよくわかりませんが、とにかく、まさに稽古真っ只中の『葵上/二重の影』という作品は、膨大な演劇的教養と、強固なアカデミズムと、伝統演劇からコンテンポラリーダンスまでを含んだ多様な身体性と、最新の技術を駆使したテクニカル(音響・映像など)が、欲張りすぎるほどぎっしり詰まった〈怪物〉のような作品で、いかに私が演出助手を勤めているからといって、それについて「もっともらしいことを書く」など、とても手に負えるお仕事ではありません。容量オーバー、思考停止であります。
まだしも『葵上』は、〈日本の伝統〉を扱っている点において、かろうじて、私自身の演劇活動のテーマと重なる部分もありますので、なんらかの形で、言及することは可能かもしれませんが、「二重の影」は、ほとんど無知。演出助手を務めるにあたって必要最低限の知識しか持ち合わせておりませんので、いよいよ困ってしまいます。
困ってばかりいても、原稿用紙の升目はいっこうに埋まってくれませんから、ここはひとつ腹を括って書くしかありません。
なので、ちょっとスタンスを変えることにします。『葵上/二重の影』という〈怪物〉をまさに産もうとしている現場の末席に加わっている木ノ下裕一が勝手に紹介する、作品をより楽しむための〈ツボ〉や〈おススメ予習方法〉。いわば非公式ガイドブックのつもりで書いてみたいと思うのです。この公演を楽しみにしてチケットをお買い求めてくださったお客様に、また、なんだか面白そう……観に行ってみようかな、と思案しておられるお客様候補の皆様に捧げます。
『葵上/二重の影』―。知れば知るほど、これほどに、〈知的好奇心〉を満足させてくれる作品、滅多にありませんよー!
『葵上』は、現代音楽家・湯浅譲二氏の「葵の上」(1961年)の録音をもとに舞台化されます。湯浅氏の「葵の上」は観世寿夫・榮夫・静夫三兄弟による同曲の謡いを電子的に変形しつつ再編集した30分の〈ミュージック・コンクレート〉ですが、まずこれだけでも聴きごたえ充分にありです。とりわけ「昭和の世阿弥」と称された名人・寿夫氏の多彩な〈声〉は、電子的に変換されず残っている部分も多く、その至芸のいったんを体感することができます。また電子的に変換し、再構成することによって、「謡曲」を〈物語〉という枠組みから一度解放し、また、言葉と、そこに常に付きまとう〈意味〉とを切り離すことによって、「ことば」そのものが持つ音曲性(音、フシ、息など)の多様さを再認識させてくれます。今回の『葵上』は、〈ことば〉を解体したミュージック・コンプレートがもたらす効果を最大限に活かしつつも、それをもう一度、〈物語〉に還元するという試みでもあるのではないでしょうか。それも重層的に、より豊穣な〈物語〉に。
舞台には、若者とシテの二人――。レーサー服に身を包んだ謎(?)の若者(茂山童司氏)が登場しますが、これは「自動車レースで瀕死の事故を起こした若者が、死にいたるまでの僅かな時間の隙に、美しい未亡人との恋を幻視する」という本作品の設定のためで、古典の『葵上』における「賀茂の祭の車争い」を「カーレース」に、「光源氏と六条御息所の恋」を「未亡人との恋」に、というふうに、現代に設定を置き換える〈知的な遊戯〉なのですね。
さて、今回の『葵上』には、いくつものテクストが使用されております。謡曲『葵上』の詞章にはじまり、古典文学『源氏物語(葵の巻)』の原文、円地文子による現代語訳『源氏物語』から「葵」、「夕顔」・・・。平安時代から現代まで生成され続けてきた、いわば「葵上」にまつわる様々なイメージを断片的にコラージュすることによって、〈恋と情念の物語〉がより多面的に描き出される仕掛けになっているのですね。『葵上』鑑賞のための第一のツボは、この複数のテクストの交錯を楽しむところにあるように思います。複数のテクストを語り分けるのは、主に若者なのですが、語り分けながら、カーレーサーであった若者が、ある時は、「怨霊を呼び出す巫女」に、またある時は「光源氏」に、「六条御息所」に、「葵上」に…と次々に姿を変えていきます。それに伴い、本行(お能)通りのシテと若者の関係も、変容していく――。まさに演劇的な醍醐味!
だから、事前に、『源氏物語』(葵、夕顔)の原文、円地訳、謡曲『葵上』にざっと目を通しておかれることをおススメいたします。基本的なストーリーを再確認する意味でも、きっとよい鑑賞の手引きになってくれるはずですよ。
見どころで、もう一つ、忘れてならないのが、高谷史郎さんによる映像。劇の進行に伴って、様々な視覚的なイメージが、舞台に設えられた二枚のパネルに映し出されます。その美しさたるや!能楽堂などでお能を見ていると、謡いの言葉から誘発されるイメージが頭一杯に広がるという体験をすることがありますよね。それを見事に視覚化したかのような映像です。「そうそう、いい能を観ている時の頭の中は、まさにこんなイメージが広がるよね!」とお思いになるはずです。
シテは、片山九郎右衛門師(29日)、観世銕之丞師(30日)のお二人によるWキャスト。これも贅沢ですね。ここだけの話……じつはお二人、それぞれ微妙に演出が異なります。その違いを見比べるのも楽しいはず。ぜひ二日ともお越しくださいませ――。
『葵上/二重の影』演出助手 木ノ下裕一(木ノ下歌舞伎主宰)
『二重の影』は、フランスの劇詩人、ポール・クローデル(1863~1955)が日本で書き上げた大長編戯曲『繻子の靴』の二日目(第二部)に挿入されている同名の「場」が元になっています。この場は戯曲形式ではなく、詩の形式をとって書かれていますが、文庫本にして二ページ足らずの場面でありながら、その内容の難解さと、展開されるイメージの壮大さから、上演することが極めて難しいとされているのだそうですよ。その〈難物〉を、クローデルの専門家でもある渡邊守章先生が演出的指揮を執りながら〈メディアパフォーマンス〉という最新のテクニカルを駆使した表現として、舞台化するのが、今回の『二重の影』です。
「二重の影」の内容はというと――ある男と人妻が熱烈な恋に落ちてしまうが、二人は海を越えて遠く離れ離れになってしまう。しかし、二人の想いは激しくて、その執念から、やがて、モロッコの白壁に二人の影だけが重なるように映し出されるようなる――。(このあたりの詳しいいきさつについては、ぜひ『繻子の靴』(渡邊守章訳・岩波文庫上下巻)をお読みください。)しかしながら、主(あるじ)のない二体の影が合体するなんて、美しくもあり、怖くもありますね。今回の『二重の影』では、そのイメージに負けず劣らぬ美しい二人のダンサー(すなわち白井剛さん、寺田みさこさん)が出演されます。特に見どころは、「二重の影」朗読に合わせて踊るシーン。言葉の持つ〈イメージ〉や〈意味〉が、次々と二人のダンサーの〈身体〉に投影され、変容していく様を目撃するのは、やっぱり至福です。古典芸能好きの私は、〈ことば〉と〈身体〉が重なったり、逆に乖離したり、ともに響き合いながら新しい「詩的な世界」を展開していくこの作品の稽古を見ながら、ふと文楽のような豊かさだな、と思ったりしております。
『葵上』に引き続き、高谷さんの映像も見どころのひとつ、『葵上』とはやや異なるテイストですので、そのあたりの変化もお楽しみください。またクラッシックから雅楽まで幅広く使用される音楽も大きな聴きどころ。特に、新進気鋭の若手音楽家・原摩利彦さんが今回のために書き下ろした新曲「モロッコの壁」は、美しくもあり奇怪でもある「二重の影」の空気感を見事に体現していると思います。ちなみに、今回、「多面体スピーカー」と呼ばれる特殊な音響機器がふんだんに使用されており、最新のテクニカルによって客席全体が〈音の海〉と化すはずです。
外交官でもあったクローデルは在日した経験もあり、日本文化にも強い関心を寄せていたのだそうです。能や歌舞伎を多く鑑賞し、また、それらについての論考も多く書き残しております(『朝日の中の黒い鳥』という日本文化論集が有名)。現にクローデル自身、「二重の影」を発想するにあたって、中国や日本に伝わる説話(恋が叶わず死した男女の執念が二本の梓の木となり、やがて二本の木が絡み合うという内容)を典拠の一つにしているそうですよ。
そう、『葵上』と『二重の影』は、単なる同時上演ではないのですね。演劇とダンス、日本古典文学とフランス文学…二つは一見、異なる出自を持った作品に見えて、根底で応答し合っているようにも感じられます。例えば、「光源氏と六条御息所」と「男女の影」、ともに〈不可能な恋〉というテーマを持っていますし、そのテーマを、歌舞伎劇場の機構や、能狂言の手法やコンテンポラリーダンスの身体性、映像、音楽、最新のテクニカルを駆使して、どう多様に、より豊かに〈表象〉し直すことができるかという、大きな実験なのだと思います。
同時にそれは、研究者と演出家の二本の道を同時に歩んでこられた渡邊守章先生が、常にお持ちになっていたであろう〈アカデミックなものを、如何に芸術に接合するか〉という命題に真っ向から挑む、集大成的な作品になるのではないかと思っております。81歳をむかえられてなお、ご自身のこれまでの業績を〈問い直す〉先生は、表現者としてサイコーにカッコよく、私の眼には映っています――。