即興といえば、今回の出演者のひとりである
山田せつ子さんが、この大学で専任教員として教えられていた時に、
笠井さんに特別授業に来ていただいたことがありましたね。
studio21で3時間ぐらいワークショップをやっていただいた。
僕はあれが非常に衝撃的で、非常に面白かったのですが。
僕の記憶が間違っていなければ、
あの時、笠井さんは学生が40人ぐらいバーっと
即興で踊っている中で、「主観は客観である!」と
繰り返し叫んでいらっしゃったと思うんですね。
とにかくそれがものすごく印象的でした。
普通に考えると、「主観は客観である」というのは、
言葉の上では矛盾しているし、「えっ、何それ?」って
感じになるはずですが、
笠井さんが踊りながらその言葉を発していると、
独特の明晰さが感じられて、
完璧に納得させられてしまったんですね。
「主観が客観である」というのは、
書き言葉のレベルであれば
哲学的な回路を通さないと分からないような命題なのに、
笠井さんのダンスだと成り立ってしまうのは、
いったいなぜだろう、と。
そういえば、さっきあげた石井さんのインタビューのなかでも、
「イマジネーションは、できるだけ客観的なものでありたい」
ということをおっしゃっているのが印象的だったのですがstudio21
春秋座と共に京都劇術劇場内にある劇場。現代演劇やダンス、パフォーマンスなど、さまざまな舞台芸術のための実験的演出が可能な空間。


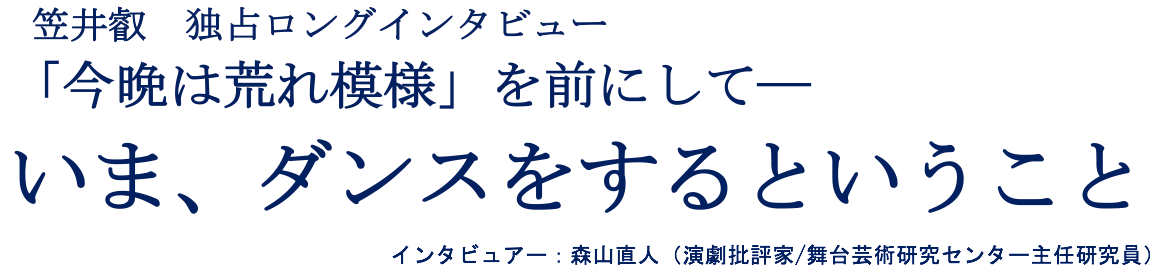

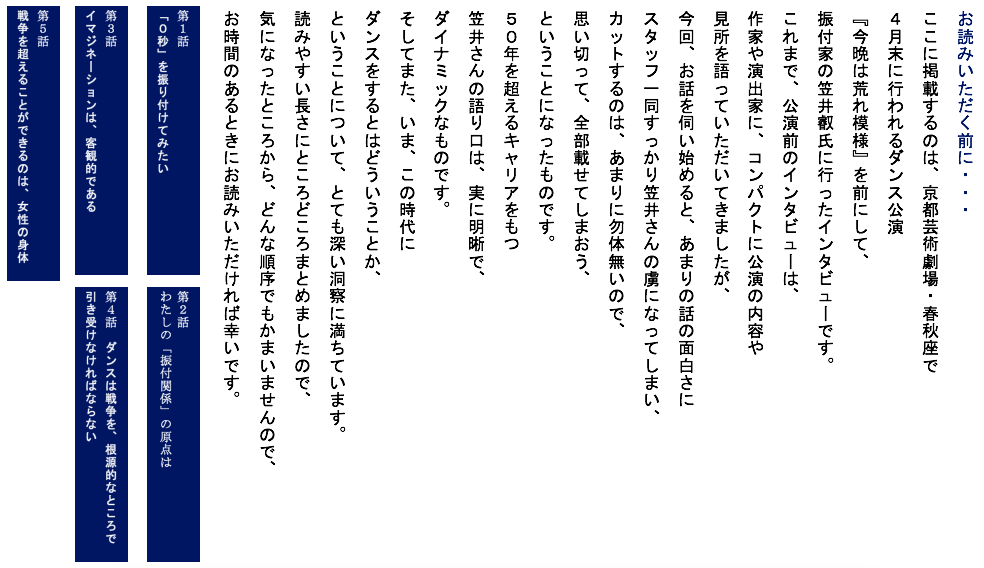
 「血は特別なジュースだ」写真:清水俊洋
「血は特別なジュースだ」写真:清水俊洋
 「病める舞姫」写真:神山貞次郎
「病める舞姫」写真:神山貞次郎

 「花粉革命」写真:清水俊洋
「花粉革命」写真:清水俊洋





